
こんにちは、hachi8833です。git.ruby-lang.orgが先週から不調なようです。
- サイト: git.ruby-lang.org
つっつきボイス:「(DevToolsを覗いて)これは大変そう… 裏でめっちゃ作業してそうな雰囲気」「お祈りします
裏でめっちゃ作業してそうな雰囲気」「お祈りします 」
」
- 各記事冒頭には
でパーマリンクを置いてあります: 社内やTwitterでの議論などにどうぞ
- 「つっつきボイス」はRailsウォッチ公開前ドラフトを(鍋のように)社内有志でつっついたときの会話の再構成です
- 毎月第一木曜日に「公開つっつき会」を開催しています: お気軽にご応募ください
![⚓]() お知らせ: 週刊Railsウォッチ「第17回公開つっつき会」(無料)
お知らせ: 週刊Railsウォッチ「第17回公開つっつき会」(無料)
第16回目公開つっつき会は、今週12月05日(木)19:30〜にBPS会議スペースにて開催されます。
週刊Railsウォッチの記事やここだけの話にいち早く触れられるチャンス!発言・質問も自由です。引き続き皆さまのお気軽なご参加をお待ちしております 。
。
![⚓]() Rails: 先週の改修(Rails公式ニュースより)
Rails: 先週の改修(Rails公式ニュースより)
先週のウォッチに載せられなかった分も含んでます 。
。
![⚓]()
params.member?を追加してHashの振る舞いに近づけた
実際はdelegateに:member?を追加しただけの改修です。
# actionpack/lib/action_controller/metal/strong_parameters.rb#L214
- delegate :keys, :key?, :has_key?, :values, :has_value?, :value?, :empty?, :include?,
+ delegate :keys, :key?, :has_key?, :member?, :values, :has_value?, :value?, :empty?, :include?,
:as_json, :to_s, :each_key, to: :@parameters
# actionpack/test/controller/parameters/accessors_test.rb#165
test "member? returns true if the given key is present in the params" do
assert @params.member?(:person)
end
test "member? returns false if the given key is not present in the params" do
assert_not @params.member?(:address)
end
つっつきボイス:「paramsでkey?が使えるならmember?もある方がいいという感じでしょうか?」「Rubyのハッシュにmember?なんてあったっけ?」「Rubyの公式ドキュメント↓を見ると、key?もmember?もinclude?もhas_key?も互いにエイリアスになってる 」「あそうか
」「あそうか 」 「それなら確かに全部使える方がいいですよね
」 「それなら確かに全部使える方がいいですよね 」「むしろなぜ
」「むしろなぜmember?だけなかったのかと 」「4つもあるとは
」「4つもあるとは 」「後からRubyに足されたとかかしら?
」「後からRubyに足されたとかかしら? 」「
」「member?使ったことないな〜 」
」
参考: instance method Hash#has\key? (Ruby 2.6.0)
![⚓]() コレクション読み込みチェックを最初のレコードではなく全レコードでチェックするよう修正
コレクション読み込みチェックを最初のレコードではなく全レコードでチェックするよう修正
現在、コレクションが読み込まれたかどうかは最初のレコードしかチェックしていない。特定のシナリオで
after_initializeフック経由でレコードをフェッチした場合、コレクションの最初のレコードは読み込まれていても残りのレコードが読み込まれていない場合がありうる。
データをフェッチするときの短絡を成功させるには、コレクション内の全レコードが読み込まれたことを検証する必要がある。
これにより、関連付けを参照するSTIがafter_initializeでプリロードに失敗する問題(#37730)が修正される。
同PRより大意
# activerecord/lib/active_record/associations/preloader.rb#L186
def preloader_for(reflection, owners)
- if owners.first.association(reflection.name).loaded?
+ if owners.all? { |o| o.association(reflection.name).loaded? }
return AlreadyLoaded
end
reflection.check_preloadable!
if reflection.options[:through]
ThroughAssociation
else
Association
end
end
つっつきボイス:「たしかにlazy loadされているとこうなる 」「
」「firstだったのをall?にして、ちゃんと最後まで読み出せるかどうかを確認するように修正したと」「short circuitはとりあえず『短絡』としてみたんですが、どう表すのがいいのか迷い中です 」「追加された以下のテストをちゃんと読めば
」「追加された以下のテストをちゃんと読めばfirstだと落ちるということがわかるんでしょうきっと 」「踏んだことないエラー
」「踏んだことないエラー 」「STIでpolymorphic associationを使った場合の
」「STIでpolymorphic associationを使った場合のafter_initializeという組み合わせか〜」
# activerecord/test/cases/associations/eager_test.rb#629
def test_preloading_with_has_one_through_an_sti_with_after_initialize
author_a = Author.create!(name: "A")
author_b = Author.create!(name: "B")
post_a = StiPost.create!(author: author_a, title: "TITLE", body: "BODY")
post_b = SpecialPost.create!(author: author_b, title: "TITLE", body: "BODY")
comment_a = SpecialComment.create!(post: post_a, body: "TEST")
comment_b = SpecialComment.create!(post: post_b, body: "TEST")
reset_callbacks(StiPost, :initialize) do
StiPost.after_initialize { author }
comments = SpecialComment.where(id: [comment_a.id, comment_b.id]).includes(:author).to_a
comments_with_author = comments.map { |c| [c.id, c.author.try(:id)] }
assert_equal comments_with_author.size, comments_with_author.map(&:second).compact.size
end
end
「#37730 issue↓を見る方が早そう」「見事歯抜けに 」「ステップ実行とかやってみたら原因追えるかも
」「ステップ実行とかやってみたら原因追えるかも 」
」
![⚓]() 初期化時に訳文をeager loadingするよう修正
初期化時に訳文をeager loadingするよう修正
訳文読み込みによる初期レスポンスの速度低下を回避するため、アプリ初期化中に訳文をeager loadingする。
同PRより大意
# activesupport/lib/active_support/i18n_railtie.rb#L13
config.i18n.load_path = []
config.i18n.fallbacks = ActiveSupport::OrderedOptions.new
+ config.eager_load_namespaces << I18n
+
つっつきボイス:「i18nの訳文を後から読み込むと一発目の表示が遅くなるので修正したと」「たしかに〜」「最初に読み込むと今度はその分Railsサーバーの起動が遅くなりますけど 」「どっちにするか選べるようにして欲しい人いそう」「
」「どっちにするか選べるようにして欲しい人いそう」「config.eager_load_namespacesにデフォルトでi18nを加えるようになったのね」
config.eager_load_namespacesは前からあったようです↓(Rails 4.0.2以降)。
「railtieに入ったということはサーバーの起動速度にちょい影響しそうではある」「i18nはヨーロッパの人なら確実に使うでしょうし」「この間正式になったGoogleのCloud Runみたいな環境で動かすRailsの起動速度を極力速くしたい人にとっては、要らんお世話なのかもしれませんけどっ 」「なるほど」「逆にGitHubみたいに既にサーバーが立ち上がった状態で普通にリクエストを受けるシステムなら事前にi18nを読み込んでおいてくれる方がレスポンス速度が安定してうれしいでしょうし
」「なるほど」「逆にGitHubみたいに既にサーバーが立ち上がった状態で普通にリクエストを受けるシステムなら事前にi18nを読み込んでおいてくれる方がレスポンス速度が安定してうれしいでしょうし 」「こっちの方が本来のRailsのユースケースなので、今回の変更はごもっともという感じ
」「こっちの方が本来のRailsのユースケースなので、今回の変更はごもっともという感じ 」
」
![⚓]()
implicit_order_columnに応じて主キーで第2ソート
# activerecord/lib/active_record/relation/finder_methods.rb#L561
def ordered_relation
if order_values.empty? && (implicit_order_column || primary_key)
- order(arel_attribute(implicit_order_column || primary_key).asc)
+ if implicit_order_column && primary_key && implicit_order_column != primary_key
+ order(arel_attribute(implicit_order_column).asc, arel_attribute(primary_key).asc)
+ else
+ order(arel_attribute(implicit_order_column || primary_key).asc)
+ end
else
self
end
end
#34480のコメントにあったように、
implicit_order_columnの現在の実装では、中で値が重複している場合に同じ順序でオブジェクトが返されるとは限らない。
このパッチは(implicit_order_columnとして設定されていない場合は)主キーを第2ソートとして追加することで出力の順序が一貫するようになった。
同PRより大意
つっつきボイス:「ここからは新しめの改修です」「むしろ#34480で足されていた元の機能↓の方が気になりますね: 自分は昔からこの機能があればいいのにって思ってましたし」「Rails 6で入ってたんですね 」
」
暗黙のorder用カラムを指定可能に
ソートのorderを明示せずにfirstやlastなどのorderありfinder系メソッドを呼ぶと、Active Recordは主キーでソートする。主キーがオートインクリメントの整数値でない場合(UUIDなど)、これによって予想外の振る舞いが生じる可能性がある。今回の変更では、firstやlastの結果が予測可能になるように、それらの暗黙のorderで使われるカラムをオーバーライドできるようになった。
#34480のActive Record Changelogより
class Project < ActiveRecord::Base
self.implicit_order_column = "created_at"
end
後で調べると、6.0リリースノートでも#34480についてはごく簡単にしか触れられていませんでした↓。
![⚓]() 6.0の
6.0のimplicit_order_columnカスタマイズ機能の使い所
「こういうふうに、ORDER BYを付けなかった場合にデフォルトで付けてくれる機能がある方が、世の中の人はおおむね幸せになれる 」「なれます〜
」「なれます〜 」「前はなかったのもびっくりですね
」「前はなかったのもびっくりですね 」
」
「ただしこの機能はケースバイケースでもあるんですよ: ORDER BYが付くとクエリが激重になることがあるから 」「インデックスがらみとか?」「というより、RDBMSにとってはORDER BYが付かない方が見つけた順に結果を返せるから総じて速くなります」「そうそうっ」「ソートは重たい操作なので、ORDER BYを付けるとクエリが最初に返り始めるまでの時間が長くなりますし」「でかいテーブルが要注意なんですね
」「インデックスがらみとか?」「というより、RDBMSにとってはORDER BYが付かない方が見つけた順に結果を返せるから総じて速くなります」「そうそうっ」「ソートは重たい操作なので、ORDER BYを付けるとクエリが最初に返り始めるまでの時間が長くなりますし」「でかいテーブルが要注意なんですね 」
」
「デフォルトでORDER BYを付けるというのは環境によっては耐え難いほどクエリが遅くなることもあるので 」「なるほど、だから機能を使うかどうかを選べるようになってるんですね」「新しいプロジェクトだったらあらかじめApplicationRecordで指定しちゃう手もありますし
」「なるほど、だから機能を使うかどうかを選べるようになってるんですね」「新しいプロジェクトだったらあらかじめApplicationRecordで指定しちゃう手もありますし 」「外すかどうかはデータが育ってから考えると」「そうそう、データが育っちゃった後でこの機能をいきなり使うと遅くて死ぬ可能性あります
」「外すかどうかはデータが育ってから考えると」「そうそう、データが育っちゃった後でこの機能をいきなり使うと遅くて死ぬ可能性あります 」「後からこの機能を使うのはコワい
」「後からこの機能を使うのはコワい 」
」
「で元の#37626は何が修正されたんでしたっけ 」「以下のAPIドキュメント↓を見ると、結果のソート順が主キーで確定するなら主キーでサブソートされるということみたい」「プルリクタイトルの『Additionally order by primary key if implicit_order_column is not uniq』とプルリクの内容が何だか微妙に食い違ってる気がする…
」「以下のAPIドキュメント↓を見ると、結果のソート順が主キーで確定するなら主キーでサブソートされるということみたい」「プルリクタイトルの『Additionally order by primary key if implicit_order_column is not uniq』とプルリクの内容が何だか微妙に食い違ってる気がする… 」「Railsに限らないと思うんですけど、プルリクのタイトルってめちゃ走り書きなことがあって、これまでも先週の改修でちょくちょくダマされました
」「Railsに限らないと思うんですけど、プルリクのタイトルってめちゃ走り書きなことがあって、これまでも先週の改修でちょくちょくダマされました 」「
」「 」「前はnon-uniqueなカラムを使うとソート順が確定しないことがあるという記述が消されてる」「created_atみたいにuniqueが保証されないカラムも指定できるようになった?」「意図がイマイチ汲み取りきれない
」「前はnon-uniqueなカラムを使うとソート順が確定しないことがあるという記述が消されてる」「created_atみたいにuniqueが保証されないカラムも指定できるようになった?」「意図がイマイチ汲み取りきれない 」
」
# activerecord/lib/active_record/model_schema.rb#L116
# Sets the column to sort records by when no explicit order clause is used
# during an ordered finder call. Useful when the primary key is not an
- # auto-incrementing integer, for example when it's a UUID. Note that using
- # a non-unique column can result in non-deterministic results.
+ # auto-incrementing integer, for example when it's a UUID. Records are subsorted
+ # by the primary key if it exists to ensure deterministic results.
「でもimplicit_order_columnがカスタマイズできるということがわかったのはうれしい 」「いいこと知った
」「いいこと知った 」「新しいRailsプロジェクトなら最初から入れといてもいいぐらい
」「新しいRailsプロジェクトなら最初から入れといてもいいぐらい 」「付けてないことによる事故の方が多かったりしますし
」「付けてないことによる事故の方が多かったりしますし 」「特に、MySQLはオートインクリメントされたカラムを割とその順序で返してくれるけどPostgreSQLはそうでなかったりしますし」「そうそうっ
」「特に、MySQLはオートインクリメントされたカラムを割とその順序で返してくれるけどPostgreSQLはそうでなかったりしますし」「そうそうっ 」「でもPostgreSQLの方がSQLとして本来の姿なんですよね
」「でもPostgreSQLの方がSQLとして本来の姿なんですよね 」「ORDERを指定しないところに順序なんかないっ
」「ORDERを指定しないところに順序なんかないっ 」
」
以下の記事によるとimplicit_order_columnではカラムを1つしか指定できないそうです。
参考: Rails6 のちょい足しな新機能を試す71(implict_order_column 編) - Qiita
![⚓]()
ConnectionAdapters::Resolverを削除
# activerecord/lib/active_record/connection_adapters/abstract/connection_pool.rb#L1042
def establish_connection(config, pool_key = :default)
- resolver = Resolver.new(Base.configurations)
- pool_config = resolver.resolve_pool_config(config)
+ pool_config = resolve_pool_config(config)
db_config = pool_config.db_config
# activerecord/lib/active_record/connection_handling.rb#L251
private
def resolve_config_for_connection(config_or_env)
raise "Anonymous class is not allowed." unless name
config_or_env ||= DEFAULT_ENV.call.to_sym
pool_name = primary_class? ? "primary" : name
self.connection_specification_name = pool_name
- resolver = ConnectionAdapters::Resolver.new(Base.configurations)
-
- db_config = resolver.resolve(config_or_env, pool_name)
+ db_config = Base.configurations.resolve(config_or_env, pool_name)
db_config.configuration_hash[:name] = pool_name
db_config
end
つっつきボイス:「ロジックが重複していたので片方を削除したのね 」「リファクタリング」「お引越し
」「リファクタリング」「お引越し 」
」
ConnectionAdapters::ResolverとDatabaseConfiguratonsという2つのオブジェクトに同じロジックが多数実装されている。一方はconfig/database.ymlで定義された設定に用い、もう一方はestablish_connectionなどのメソッドにStringやHashで生の設定を渡すのに用いる。
時間とともに2つのロジックが少し乖離してきたので、コードの複雑さを軽減して一貫性を高めるためにResolverを削除して主なメソッドをDatabaseConfigurations#resolveに置き換え、resolve_pool_configをConnectionPoolに移動するなどした。
同PRより大意
「ついでにdatabase.ymlに関するAPIドキュメントがちょっと足されているみたい↓」「お〜 」「こうやってコメントがちゃんと書かれるとありがたい
」「こうやってコメントがちゃんと書かれるとありがたい 」
」
# activerecord/lib/active_record/connection_adapters/abstract/connection_pool.rb#L1149
# Returns an instance of PoolConfig for a given adapter.
# Accepts a hash one layer deep that contains all connection information.
#
# == Example
#
# config = { "production" => { "host" => "localhost", "database" => "foo", "adapter" => "sqlite3" } }
# pool_config = Base.configurations.resolve_pool_config(:production)
# pool_config.db_config.configuration_hash
# # => { host: "localhost", database: "foo", adapter: "sqlite3" }
#
![⚓]() Rails
Rails
![⚓]() rubocop-rails 2.4.0がリリース
rubocop-rails 2.4.0がリリース
つっつきボイス:「rubocop-railsは本家rubocopとバージョンの歩調を合わせないことにしたという話がありましたね」「そうそう、本家に構わずガンガン上げていくぜと 」
」
新機能:
Rails/ApplicationControllercopとRails/ApplicationMailercopを追加Rails/RakeEnvironmentcopを追加Rails/SafeNavigationWithBlankを追加
![⚓]() Rails機能のエンジンへの切り出しにRuboCopを活用
Rails機能のエンジンへの切り出しにRuboCopを活用
つっつきボイス:「Railsエンジンの切り離し?」「上の図↑はエンジンのデータを自由に読み書きできちゃまずいよねという話みたい」「ちゃんとしたインターフェイスを経由してやりとりしないと 」
」
「isolate_namespace↓ってあったそういえば」「おぉ?」「これを使うことで名前空間が分かれる: エンジンを書くときはこうしないとRails側とかぶっちゃうとか何とかだったと思う」「きっとRailsガイドにある気がします 」「マウンタブルエンジンについては丁寧なガイドがあるはず
」「マウンタブルエンジンについては丁寧なガイドがあるはず 」「密結合したエンジンなんてエンジンじゃないし
」「密結合したエンジンなんてエンジンじゃないし 」「
」「 」
」
参考: 2.1.1 重要なファイル — Rails エンジン入門 - Rails ガイド
Engineクラスの定義に含まれる
isolate_namespaceの行を変更・削除しないことを強く推奨します。この行が変更されると、生成されたエンジン内のクラスがアプリケーションと衝突する可能性があります。
Railsガイドより
「Railsアプリが太ってきたときにどう分割するかという方法はいくつかあるんですが、そのひとつが機能のエンジン化ですね」「おぉ」「複数のRailsアプリにする方法とは別に、1つのRailsアプリの中でエンジンに切り出すという方法 」「記事を書いた人は、その辺の作業を支援するためにcopをいくつか作ったみたいです↓」「危ないときに立ち会ってくれるcop
」「記事を書いた人は、その辺の作業を支援するためにcopをいくつか作ったみたいです↓」「危ないときに立ち会ってくれるcop 」「マウンタブルエンジンとかそんなにしょっちゅうは書かないから
」「マウンタブルエンジンとかそんなにしょっちゅうは書かないから 、そういうのがあるとよさそう」
、そういうのがあるとよさそう」
記事では、他の切り離し方法として「リードオンリーActive Record」や「明示的に定義された依存関係だけをテストで読み込む」「Active Recordのsaveなどにフックをかける」なども紹介されています。
![⚓]() Bundlerを健全に使うには
Bundlerを健全に使うには
# 同記事より
# 正確なバージョン指定
gem 'nokogiri', '1.0.3'
gem 'webrat', '0.3.1'
# ペシミスティックなバージョン指定
gem 'nokogiri', '~> 1.0.3'
gem 'webrat', '~> 0.3.1'
# バージョン指定なし
gem 'nokogiri'
gem 'webrat'
つっつきボイス:「2012年という古い古い記事ですが、先週出した翻訳記事↓で言及されていたので」「gemのバージョンをきっちり指定する場合とかペシミスティックに指定する場合とかについての話ね 」
」
「ところで、gemとかのバージョンをピンポイントに指定するのって、それはそれでたまにリスクがあったりするんですよ」「マジですか?! 」「ピンポイントに指定したバージョンが何かのミスで消えちゃったりしたら当然失敗するようになるので
」「ピンポイントに指定したバージョンが何かのミスで消えちゃったりしたら当然失敗するようになるので : もっとも最近はそういうことはあまりありませんけど
: もっとも最近はそういうことはあまりありませんけど 」
」
「上の翻訳記事の方ではJSのモジュールのバージョンを全部ピンポイントにしないと気が済まないという感じでした」「Rubyもそうですけどね 」「ただGemfile.lockにはピンポイントで書かれてそちらが正ですけど、Gemfileの方にはこのぐらいのバージョンなら動くよねという期待を込めてバージョンを書いたりしますし
」「ただGemfile.lockにはピンポイントで書かれてそちらが正ですけど、Gemfileの方にはこのぐらいのバージョンなら動くよねという期待を込めてバージョンを書いたりしますし 」「最近もGCPのgemがめちゃ古くないと動かないケースあった…
」「最近もGCPのgemがめちゃ古くないと動かないケースあった… 」
」
![⚓]() Capistranoを使う(Ruby Weeklyより)
Capistranoを使う(Ruby Weeklyより)
# 同記事より
# lib/capistrano/tasks/login.rake
desc "Login into a server based on the deployment stage"
task :login do
on roles(:app) do |server|
user = fetch(:user)
path = fetch(:deploy_to)
uri = [
user,
user && ‘@’,
server.hostname,
server.port && “:”,
server.port
].compact.join
end
end
つっつきボイス:「こっちは新しくて普通にCapistranoやった記事ですが、Capistranoの新しい記事というのが珍しそうだったので」「そうそう、Capistranoの記事って意外に少ない 」「記事書いた人もきっと同じ思いだったに違いない
」「記事書いた人もきっと同じ思いだったに違いない 」「『ないなら自分で書くわい』みたいな
」「『ないなら自分で書くわい』みたいな 」「これは翻訳したいです
」「これは翻訳したいです 」
」
「Capistranoのコードを書く人は、どちらかというとサーバーサイドのインフラエンジニアですよね: 書き方はいろいろだけど、いったん書き方が枯れて安定してしまえばそれで全然いいという感じですし 」「インフラエンジニアがCapistranoコードでテンプレートを一度がっつり書いておけば、後はみんなでそれを使い回す
」「インフラエンジニアがCapistranoコードでテンプレートを一度がっつり書いておけば、後はみんなでそれを使い回す 」「秘伝のタレ的なconfigがあったりしますね
」「秘伝のタレ的なconfigがあったりしますね 」「実際Capistrano自体もそんなに変わってませんし
」「実際Capistrano自体もそんなに変わってませんし 」
」
前編は以上です。
バックナンバー(2019年度第4四半期)
週刊Railsウォッチ(20191125)Ruby 3.0は2020年12月にリリース決定、Rails 5.2.4rc2とRuby 2.7.0-preview3がリリースほか
- 20191119後編 メソッド参照演算子が廃止、GitHub新機能続々、平成Ruby会議、GitHub OAuthバイパスほか
- 20191118前編 ActiveJob引数のログ抑制、RailsガイドProプランお試し、ファイルアップロードのレジュームgemほか
- 20191112後編 invisible gemで可視性を変えずにパッチ当て、スライド:「型なし言語のための型」、自然言語の言語名を推測ほか
- 20191111前編 Active Recordモデルをprivateで封じ込める、心折れないRailsスキーマ管理、Railsセッションをクロスドメイン共有ほか
- 20191106後編 holiday_japan gemで日本の祝日判定、小さい関数が有害になるとき、Gitブランチのファジー検索ほか
- 20191105前編 Rails 6のデフォルト設定解説、DHHも消したいaccepts_nested_attributes_for、スライド『実践Railsアプリケーション設計』ほか
- 20191029後編 Ruby 2.7.0-preview2、tapping_device gemとhumanize gem、平成Ruby会議ほか
- 20191028前編 RailsにSTI用メソッドsti_class_forとpolymorphic_class_forが追加、RuboCopを変更箇所だけにかけるgem、strftime書式生成サイトほか
- 20191021 Rails 6でhas_many関連の修正やSprockets 4.0対応、Shrine 3.0がリリース、Minitestスタイルガイドほか
- 20191015 スライド「Rails Performance issues and Solutions」を見る、dirtyに*_previously_was が追加、Sidekiq 6.0.1ほか
- 20191008後編 Ruby 2.7のInteger#[]でバイナリチェック、rubyzip gemは強力、13KBのJavaScriptゲームほか
- 20191001後編 RedisとRubyをつなぐredis-object gem、Fullstaq Rubyの新バージョン、COUNT(*)とCOUNT(1)の速度ほか
今週の主なニュースソース
ソースの表記されていない項目は独自ルート(TwitterやはてブやRSSやruby-jp Slackなど)です。
 でパーマリンクを置いてあります: 社内やTwitterでの議論などにどうぞ
でパーマリンクを置いてあります: 社内やTwitterでの議論などにどうぞ









 」「使うかどうかわからんけどっ
」「使うかどうかわからんけどっ

 」「こういうイベントをずっと継続しているのはエライ!」
」「こういうイベントをずっと継続しているのはエライ!」
 」「そういえばこんな記事もありましたね↓」
」「そういえばこんな記事もありましたね↓」

 」「zero dependencyの何がうれしいって、他のライブラリのコードを気にしなくてよくなることですね
」「zero dependencyの何がうれしいって、他のライブラリのコードを気にしなくてよくなることですね 」「そうそうっ
」「そうそうっ




 」「その技術自体は以前から存在してますけど、それを安全にやるのはかなり難しいでしょうね〜
」「その技術自体は以前から存在してますけど、それを安全にやるのはかなり難しいでしょうね〜
 」「
」「















 」
」
 」「おぉ」「その分バイナリのサイズはでかくなりますけど、その代わり同じOSならライブラリ構成とかが全然違っていても入れるだけで動かせます
」「おぉ」「その分バイナリのサイズはでかくなりますけど、その代わり同じOSならライブラリ構成とかが全然違っていても入れるだけで動かせます
 」
」

 」
」





 」(以下延々)
」(以下延々)

 」「Slackのオートフォーマット機能のせいでこれまでどんだけ生産性が落ちていたかと
」「Slackのオートフォーマット機能のせいでこれまでどんだけ生産性が落ちていたかと 、最近だとベルの代わりに画面が一瞬ピカッと光るとかもありますね
、最近だとベルの代わりに画面が一瞬ピカッと光るとかもありますね 」
」 」
」 。ありがとうございます!
。ありがとうございます! (@tkmkg8m)
(@tkmkg8m) 





 」「よろしくお願いしま〜す
」「よろしくお願いしま〜す


 」「スライドもいろいろ上がってくると思いますので楽しみ
」「スライドもいろいろ上がってくると思いますので楽しみ

 あったので」「最近地味に進められている、不要な
あったので」「最近地味に進められている、不要な




 Rails
Rails (@Yuppyhappytoyou)
(@Yuppyhappytoyou) 





 」「そうそう皆さん、4月はRubyKaigiですよお忘れなく
」「そうそう皆さん、4月はRubyKaigiですよお忘れなく

 」「誰か分かる人?」「わかりません
」「誰か分かる人?」「わかりません
 」「しかもWAFが原因であることを突き止めるのが大変ですし
」「しかもWAFが原因であることを突き止めるのが大変ですし 」
」






 」「そういえば以前も話題に出ましたね(
」「そういえば以前も話題に出ましたね( 」「OriHimeをずらり居酒屋に並べる感じで
」「OriHimeをずらり居酒屋に並べる感じで







 全てが釘に見える (@coe401_)
全てが釘に見える (@coe401_) 

 。数日前まではrdocなどドキュメントの更新が増えてリリース間近かと思いきや、
。数日前まではrdocなどドキュメントの更新が増えてリリース間近かと思いきや、


 by
by  via
via 






 (@RailsGuidesJP)
(@RailsGuidesJP) 

 」「大昔の電卓ってこれでした
」「大昔の電卓ってこれでした
 。
。 Artichoke is a Ruby made with Rust
Artichoke is a Ruby made with Rust
 (
( )。
)。
 。2020年代も週刊Railsウォッチをよろしくお願いします
。2020年代も週刊Railsウォッチをよろしくお願いします (@homkon6263)
(@homkon6263)  : 一応昨年12月26日にリニューアルしたんですけどね
: 一応昨年12月26日にリニューアルしたんですけどね 」「
」「 でパーマリンクを置いてあります: 社内やTwitterでの議論などにどうぞ
でパーマリンクを置いてあります: 社内やTwitterでの議論などにどうぞ

 」「Active Storageでvariantが使えるようになってる?
」「Active Storageでvariantが使えるようになってる? 」「Rails 6で入ってたと思います(
」「Rails 6で入ってたと思います( 」「たしかに」「画像をバンバン扱うようなシステムではこの辺が大事
」「たしかに」「画像をバンバン扱うようなシステムではこの辺が大事 」
」 」「あ〜」「bigとsmallに後からmiddleを足すとか
」「あ〜」「bigとsmallに後からmiddleを足すとか 」「Shrineは評判もいいですね」「欲しい機能はひととおりあるしメンテもされてますし
」「Shrineは評判もいいですね」「欲しい機能はひととおりあるしメンテもされてますし

 」「下の書き方の方が好き
」「下の書き方の方が好き 」「rubocopのチェックとかも効きやすいでしょうし
」「rubocopのチェックとかも効きやすいでしょうし 」「
」「 」「default.ymlを更新するとproductionで上書きされて反映されなかったりするというのがありがちなパターン
」「default.ymlを更新するとproductionで上書きされて反映されなかったりするというのがありがちなパターン 」
」 : こういうconfigはgemとかでカスタマイズされてることもよくあるので」「う〜む
: こういうconfigはgemとかでカスタマイズされてることもよくあるので」「う〜む 」「こんな変更をあっさりマージしちゃって大丈夫?っていう気持ちにちょっとなりますね…」「ちょっとドキドキする
」「こんな変更をあっさりマージしちゃって大丈夫?っていう気持ちにちょっとなりますね…」「ちょっとドキドキする 」「ドキドキする
」「ドキドキする 」「まあRails 6でやるならもうSprocketsのことは忘れてWebpackしか存在しない世界だと思って進めるのがいいんじゃないでしょうか
」「まあRails 6でやるならもうSprocketsのことは忘れてWebpackしか存在しない世界だと思って進めるのがいいんじゃないでしょうか
 」
」 」「言語のせいにしてはいかんと
」「言語のせいにしてはいかんと )
) 」「特集1はたしかに初心者向けだけど特集2のWebpack/Sprocketsあたりから急にレベル高くなってる
」「特集1はたしかに初心者向けだけど特集2のWebpack/Sprocketsあたりから急にレベル高くなってる 」
」
 ドレッシングが絶品
ドレッシングが絶品

 (@nappan23)
(@nappan23) 

 」「21:00になったら飲み食いしながらウォッチドラフトを眺めましょうか
」「21:00になったら飲み食いしながらウォッチドラフトを眺めましょうか 」「WSL2が出た後の世界で使うことがあるかどうかですけど
」「WSL2が出た後の世界で使うことがあるかどうかですけど 」「今の請求項目はダミーみたいですけどもう少ししたら本気出すみたいです」「そういえばAWSのEIPだと、使っているIPは無料で使ってないIPは有料ですね
」「今の請求項目はダミーみたいですけどもう少ししたら本気出すみたいです」「そういえばAWSのEIPだと、使っているIPは無料で使ってないIPは有料ですね


 TypeScriptが好き (@suin)
TypeScriptが好き (@suin) 
 」「お、こんなのあるんですね」「キレイなものを作るには相当気合が必要ですけどって学生にも言いましたし
」「お、こんなのあるんですね」「キレイなものを作るには相当気合が必要ですけどって学生にも言いましたし
 」「
」「 」(以下延々)
」(以下延々)
 」「映画の方が進んでるかと思ってました」「状況に合わせて最適に振る舞う手法はやっぱりゲーム業界が進んでると思いますね
」「映画の方が進んでるかと思ってました」「状況に合わせて最適に振る舞う手法はやっぱりゲーム業界が進んでると思いますね






 Eliminate deprecations from your codebase
Eliminate deprecations from your codebase  」「2.7はまだ様子見と決めてますっ
」「2.7はまだ様子見と決めてますっ 」「複合キーとか使う場合はstructure.sqlにするってガイドに載ってる
」「複合キーとか使う場合はstructure.sqlにするってガイドに載ってる 」「Railsのマイグレーション機能でサポートされていないRDBMSの機能を使うのであればそうなりますね
」「Railsのマイグレーション機能でサポートされていないRDBMSの機能を使うのであればそうなりますね






 」
」


 」
」


 」「冬の富山といえばブリでしょう
」「冬の富山といえばブリでしょう 」「まだ行ったことなくて
」「まだ行ったことなくて
 : 自分の認識では
: 自分の認識では 」「まあまあ
」「まあまあ
 」
」


 RSVP
RSVP 
 」「自分もこのお題で書いてみようかな?
」「自分もこのお題で書いてみようかな? 」「なるほど〜」
」「なるほど〜」
 ︎ JavaScript
︎ JavaScript
 」「rubygemsにもbundlerにも依存せずにbundlerと同じような感じでやれるようで、スライドにもこのgemから学ぶべきとありますね」「まあ今はbundlerとrubygemsが統合される流れになってますけど」「現状だとメンテが大変という話が先週もありましたね(
」「rubygemsにもbundlerにも依存せずにbundlerと同じような感じでやれるようで、スライドにもこのgemから学ぶべきとありますね」「まあ今はbundlerとrubygemsが統合される流れになってますけど」「現状だとメンテが大変という話が先週もありましたね(


 : 当たってる予想もあればそうでないのもあったりして結構面白いですよ
: 当たってる予想もあればそうでないのもあったりして結構面白いですよ

 」「(
」「( 12/25日発売!サービスリリースの本出版されました (@dala00)
12/25日発売!サービスリリースの本出版されました (@dala00) 
 』みたいなノリで運営されてたりしますけど
』みたいなノリで運営されてたりしますけど 」「このスケールで観測できたのがスゴい
」「このスケールで観測できたのがスゴい
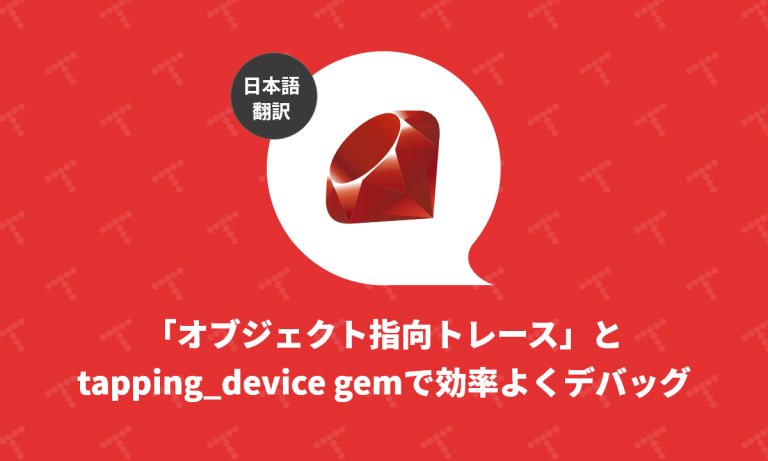






 」
」

